災害に強く、新たなまちを支える復興道路・復興支援道路
東日本大震災から10年が経過し、節目の年に全線開通
~ 沿線における工場立地の加速、地域産業を支援~
~ 交通量が全路線で増加、被災地の物流を支援~
復興道路・復興支援道路は、復興のリーディングプロジェクトとして震災後10年で全線開通させ
国土交通省東北地方整備局プレスリリースより引用
ることを目標に始動しました。
三陸沿岸道路や東北横断自動車道(釜石~花巻)など、震災時点で開通していた区間は、
わずか173km(約3割)で、主要都市間の移動はおもに現道を利用していました。仙台から八戸
間の時間は8時間35分を要していました。
復興道路・復興支援道路は、一刻も早い復旧・復興を目指し、災害に強く、新たなまちを支える道
路として、約10年で全線開通(550km)を実現しました。
広域的な道路ネットワークの完成で主要都市間の所要時間が短縮し、津波浸水区域の回避や復興ま
ちづくりと一体となったインターチェンジ配置などにより、沿線では様々な効果が発現されています。
1.沿線における工場立地の加速・地域産業を支援
○青森・岩手・宮城では、復興道路・復興支援道路沿線に新たに工場が245 件立地
○福島県内では、復興支援道路沿線の相馬港エリアに新たに工場が13 件立地
2.沿線の「道の駅」等により、復興まちづくりとしての拠点を支援
○沿線における21 箇所の道の駅を、道路上からの案内を充実し休憩サービス等を提供
・震災以降、10 箇所の道の駅がオープン(うちリニューアル5 箇所含む)
3.全線開通後の交通状況
○交通量は全路線で増加、特に大型車交通量の伸びが大きく被災地の物流を支援
・三陸沿岸道路では、特に岩手県内の大型車交通量が1.3 倍~1.7 倍増加
○三陸沿岸道路は、冬期においても信頼性の高い機能を確保
・東北自動車道が吹雪による通行止め時に、大型車約2,000 台が三陸沿岸道路に転換
○沿線市街地において交通混雑が緩和
・宮城県気仙沼市内の幹線道路では、混雑区間が約44%から約2%まで減少
○実際に走行した車両のデータ(ETC2.0 データ)を用いて、走行時間を分析
・仙台港北IC~八戸南IC 間の走行時間は約4 時間30 分
復興道路・復興支援道路について
○ 震災時点で開通している復興道路・復興支援道路の延長は約173kmで総延長550km
のわずか31%であった
○ 震災前は、仙台から八戸間の移動は8時間35分を要していたが、開通により約3時間
短縮になり5時間13分。各主要都市間の所要時間が大幅に短縮
_ページ_02-720x1024.jpg)
〇災害に強い道路とするため、強靱性の確保と防災機能の強化を実現
〇新たなまちづくりと暮らしを支える道路として、インターチェンジを弾力的に配置。地域の
産業・商業施設、防災拠点や医療施設へのアクセス性を強化して復興まちづくりを支援
_ページ_03-724x1024.jpg)
○青森・岩手・宮城では、復興道路・復興支援道路沿線に新たに工場が245件立地
○宮城県気仙沼市では効率的な流通体制を目指して共同トラックターミナルを整備。三陸沿岸道路より運送事業者6社が配送
○IC近郊に水産加工団地が集積、工場立地の約7割を占める水産加工業の出荷額も回復の兆しがみられ、地域産業の復興を支援
_ページ_04-1024x724.jpg)
○復興支援道路の相馬港エリアでは、東日本大震災以降に発電所やLNG基地など大規模施設が13件新増設
○相馬市・新地町周辺の製造業従事者が増加傾向。東北中央自動車道(相馬~福島)の開通による時間短縮により通勤圏域も拡大
○東北中央自動車道沿線の福島市・伊達市・桑折町では、交通アクセス性の向上によりIC近郊に新たな工業団地等の整備が進行中
_ページ_05-1024x724.jpg)
〇復興道路・復興支援道路沿線における21箇所の道の駅について、道路上からの案内を充実し休憩サービス等を提供
〇岩手県久慈市の新たな広域道の駅の開業予定や「大谷海岸」「高田松原」などがリニューアルオープンし、賑わいを創出
○沿線にある震災伝承施設へのアクセスが向上し、教育旅行で多く利用されるなど見学エリア、見学時間が拡大
_ページ_06-1024x724.jpg)
○ 復興道路・復興支援道路整備後の交通量は全路線で増加し、被災地の交流拡大を支援
○ 三陸沿岸道路では、特に宮城県内の交通量が大幅に増加(浦島大島IC~気仙沼港IC 約3,000台増)
○ 東北中央自動車道では、現道の隘路区間通行が回避され、内陸部と沿岸部の結びつきが強まり、
交通量が約2.4倍に増加(相馬山上IC~相馬玉野IC 約3,300台増)
_ページ_07-724x1024.jpg)
○ 復興道路・復興支援道路の整備後、特に大型車交通量の伸びが大きく、被災地の物流を支援
○ 三陸沿岸道路では、特に岩手県内の大型車交通量が1.3倍~1.7倍に増加
○ 東北横断自動車道釜石秋田線では、内陸部の工業集積地と釜石港の結びつきが強まり、
大型車交通量が約1.6倍の増加(遠野住田IC~遠野IC 約700台増)
_ページ_08-724x1024.jpg)
○吹雪による東北自動車道の通行止め時に、三陸沿岸道路の交通量は最大約1.6倍に増加(岩手県田野畑地区)
○大型車は約2,000台が東北自動車道から三陸沿岸道路に転換し、冬期でも信頼性の高い機能を確保
_ページ_09-1024x724.jpg)
○復興道路・復興支援道路の開通により、沿線市街地の交通混雑が緩和
○宮城県気仙沼市内の幹線道路では、夕方時における速度20km/h以下の混雑区間が約44%から約2%まで減少
〇岩手県宮古市内の幹線道路では、夕方時における速度20km/h以下の混雑区間が約53%から約6%まで減少
_ページ_10-1024x721.jpg)
○ 実際に走行した車両のデータ(ETC2.0データ※)を用いて、走行時間を分析
○ 仙台港北IC~八戸南IC間の走行時間は、約4時間30分
※車載器のGPSなどから経路情報や速度情報等を把握できるビッグデータ
_ページ_11-724x1024.jpg)




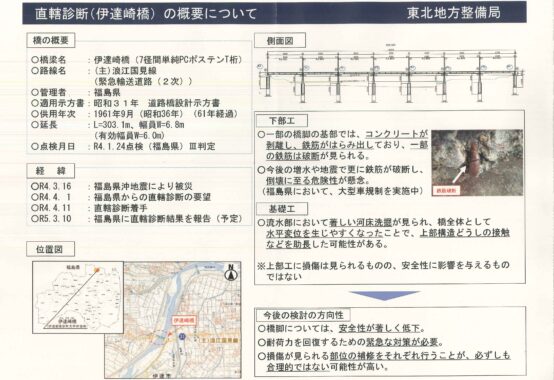


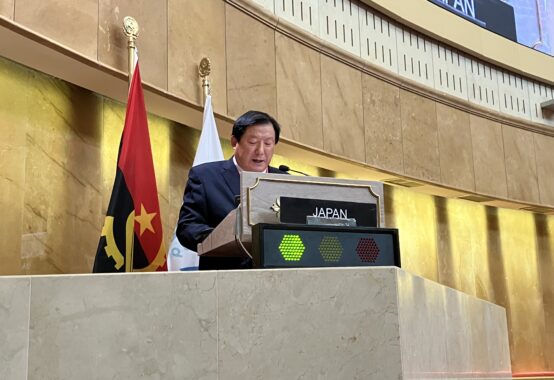

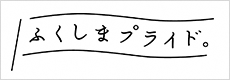
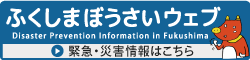



この記事へのコメントはありません。